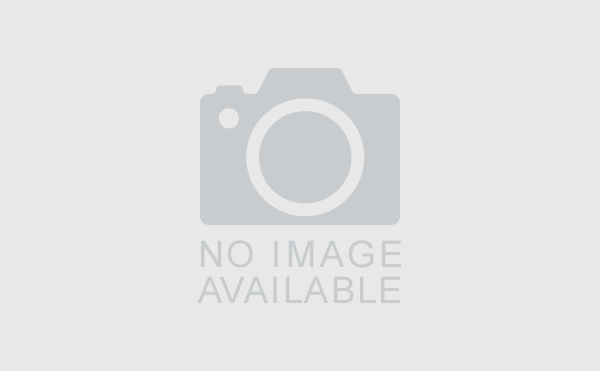NC自動旋盤加工を支えるのは“仕組み”より“空気感”なのかも
──町工場の連携力と気づきの現場
「町工場って、やっぱり少人数でやってるから大変でしょ?」
そう聞かれることがあります。実際その通りなんですが、人数が少ないこと=弱みとは一概に言えないなと感じています。
むしろ、少ないからこそ連携がしやすい。空気感でつながっている感じがある。
そしてそれが、**品質や対応力を支える“見えない力”**になっている──
そんなふうに思ってます。
現場の“気づき”が、品質を支えている
うちでは、検査員や加工担当が「ちょっとおかしいな」と思ったとき、
すぐに声を掛け合える空気があります。
段取りや寸法、切粉の様子まで、日々の変化を “言いやすい関係性” の中で共有していく。
チェックリストは大事ですが形式ばっていては無意味になる。ちょっとした声かけがミスを防ぐ。
それが積み重なって、±0.005mmの精度と、月産120万個以上でも不具合件数が年間5件という品質を維持できています。
少人数だからこそ、“誰かの気づき”がすぐ活かせる
誰が担当かより、「誰が最初に気づけたか」で動けるのが、町工場の強みかもしれません。
たとえば──
- 検査の途中で「あれ?これロット違くない?」と出荷担当が気づく
- 加工中に「この材質、いつもより硬いな」とすぐ共有が入る
“気づいたら、すぐ声に出せる”
その連携こそが、うちの一番の武器です。
お客様とのやりとりも、“近さ”より“濃さ”
鳥取という場所柄、ほとんどのお客様は遠方です。
商談もTEL、メール、リモート中心。それでも「距離を感じないですね」と言ってもらえることがあります。
それは、おそらく普段のやりとりの中で、
- 仕様確認の一言
- 加工方法の提案
- 懸念点のフィードバック
…そういった 細かな“気遣い”と“濃度” を、きちんと積み重ねているからだと思っています。
空気感でつながる現場を、これからも
うちは仕組みやシステムが充実しているわけではありません。
でも、空気を読んで、声を掛け合って、自然に連携できる
そんな現場の空気感が、今の品質を支えてくれています。
少人数でも、遠方でも、ちゃんと“応えられる加工屋”でいたい。
それは、目に見えない“空気感”が生む、現場の底力だと信じています。
次回予告?(笑)
「図面の読み方、ちゃんと伝わってますか?」
発注側と加工側でズレやすい“読み方のクセ”と、そのすり合わせの工夫についても、次回書いてみたいと思います。